ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は「2024年 日帰り勝浦(千葉県)旅行記」後編をお届けします。
★ 前編は こちら ★
千葉・勝浦を歩いて半日観光
2024年7月20日の朝8時、千葉県の勝浦駅にやって来ました。ここからはお昼過ぎまでの約半日、勝浦を歩いて観光します。
まずは駅から10分ほどの場所で開催されている朝市へ。毎月1日~15日は遠見岬神社前の通り「下本町朝市通り」、16日~月末は高照寺前の通り「仲本町朝市通り」で開催されています。

開催時間は午前6時半頃~午前11時頃まで。なお、毎週水曜日は定休日です。

今回私は電車で勝浦にやって来ましたが、駐車場(有料)も用意されており、観光客が多く訪れていることが伺えます。

朝市が開催されている仲本町朝市通りに到着。勝浦市観光協会によると、勝浦で朝市が始まったのは1591年のこと。この地の領主となった勝浦城主・植村土佐守泰忠が、漁業と農業を奨励するとともに、生産物を交換する場として開設したそうです。

仲本町朝市通り沿いにある高照寺(1480年建立)には、「勝浦朝市発祥之地」の木碑が立っています。当社はこの神社の境内で、生産物の交換が行われていたのでしょう。
勝浦朝市の歴史
勝浦市内にある覚翁寺には、泰忠の出した勝浦朝市の定書が奉納されているそうです。

これによると、酒の売買は勝浦城下だけに限定。さらに、勝浦で市が開かれる日は、近郊の松部・串浜・川津・新官(しんが)・吉宇での市の開催を禁じるなど、勝浦城下の整備にあたり、市の開設を重要視していたとされています。
■ 参考:1

一方、勝浦市観光協会のホームページでは、朝市が始まった当時「365日、いかなる天候でも朝市が開かれた」と紹介されています。しかし、定書に従うと、毎日勝浦で市が開催されてたら、他の場所で市が出来ません。勝浦朝市の始まりについては、恐らく諸説あるのでしょう。
「勝浦三町江戸勝り」とは
江戸時代の勝浦は「勝浦三町江戸勝り」と言われるほど繁栄したそうです。この言葉が「いつ」「誰が」言ったのかは不明ですが、勝浦発展の背景には、2つの事象があると考えられます。
その1. 漁業の発展

江戸時代、黒潮と親潮のぶつかる房総沖が漁場として注目されると、関西漁民による出稼ぎ漁業が行われ、さまざまな漁業技術がもたらされたそうです。
■ 参考:2

現在も、勝浦漁港は銚子漁港と並ぶ県内トップクラスの漁獲額で、外房漁業の拠点となっています。特にカツオの水揚げは盛んで、黒潮の勢力が増す3月上旬から6月半ばまでは、地元の漁船だけでなく、鹿児島や宮崎・高知などの大型漁船も勝浦沖で操業し、勝浦で水揚げするそうです。
■ 参考:黒潮とは何か
その2. 東回り航路の開設

江戸時代、太平洋沿岸を通る東廻り航路が開設されると、早くから小湊(現・鴨川市)が東北諸藩の廻船の寄港地として利用され、廻船役所(番所)や船宿が設けられるなど、海上交通の要所となりました。
■ 参考:東回り航路について

しかし、元禄16年(1703)の大地震・津波によって小湊が甚大な被害を受けると、廻船関連施設の多くが興津(現・勝浦市興津地区)へと移転。その後、廻船の寄港地や補給地としての役割が勝浦に集中するようになったことで、勝浦の発展の基礎が築かれたと考えられています。
■ 参考:3

「元禄地震の津波ここまで」という標識もありました。なお、各地に残る供養碑、墓碑、古文書に記された記録などを頼りに、元禄地震の被害について多くの研究が行われていますが、現在のところ被害の大きさは確定されていないそうです。
■ 参考:4
日本三大朝市を満喫

勝浦ではごく小規模な市が続きましたが、道路網の整備や鉄道の開通などで人や物資の流通が盛んになるにつれ、朝市も活況を示すようになりました。現在は「日本三大朝市」のひとつに数えられますが、毎朝開かれるようになったのは、明治時代以降と言われています。

こちらは歩いているときに見つけた、朝市への出店を呼びかける広告。「時代の変化の中で、朝市の出店者も多様化しています」と書かれている通り、鮮魚・干物・野菜・果物・草花だけでなく、フード・カフェ・雑貨・民芸品・アートなど、ジャンルは幅広く、土日祝は45店ほどの店が並んでいます。

特に行列が出来ていたのは、南蛮屋のわらび餅。たこ焼きに使う舟形の器に盛られるわらび餅は、勝浦朝市の名物となっています。

そして、私の戦利品(朝食)がこちら。わらび餅だけでなく、ご飯と総菜、日本酒とおつまみもゲットしました。そう、朝市なのにお酒も提供されているのです。

2種類の地酒と「のしいか」が付いて、確か900円だった気がします。
〇
のしいかは、注文するとその場で炙っていただけるスタイル。座って休める場所も用意されており、朝市には1時間ほど滞在しました。
遠見岬神社
時刻は9時半過ぎ。太陽が昇って来ると、さすがの勝浦でも暑いです。

続いてやって来たのは遠見岬神社。阿波国(徳島県)から黒潮にのって房総半島へ辿り着いた後、関東地方を開拓したとされる天冨命(あめのとみのみこと)を祀る神社で、その由緒は初代天皇・神武天皇の時代に遡ります。

神社へと続く石段は「冨咲の石段」と呼ばれており、この石段を上ると「富が咲き幸せになる」と伝えられているとか。約40万人もの観光客が訪れる「かつうらビッグひなまつり」では、石段に1200体のひな人形が並びます。

江戸時代までは富大明神と称し、はじめ八幡岬突端(現在は勝浦城址付近)にあったといわれていますが、1601年の津波で流され、現在の地に遷座されたのは1659年のこと。現在の社殿は1849年に造営されたものと紹介されています。
■ 参考:5

以前にTBSの番組「マツコの知らない世界」で、『開運神社15選』のひとつとして紹介されたそうです。

こちらが遠見岬神社からの景色。勝浦の中心地を一望することが出来ます。最後に向かうのは、市街地に隣接する勝浦中央海水浴場です。
勝浦中央海水浴場
遠見岬神社から歩いて約10分、勝浦駅からも歩いて約10分の場所に位置する海水浴場です。

海水浴場へと向かう前に、遠見岬神社のおみくじをゲット。男性向けの勝男(かつお)みくじと、女性向けの金女(きんめ)みくじがあり、いいお土産になります。

ということで、海水浴場に到着。GoogleMapでは「勝浦中央海水浴場」と表示されていますが、勝浦市のホームページでは「勝浦中央海岸」と紹介されており、海水浴場として開放はされていないようです。

綺麗な海と海岸ですが、確かに泳いでいる人はいません。しばし海辺でのんびり…と思いましたが、日差しを遮るものがないので、やはり暑いです。それほど長居はせず、駅へと戻りました。今回の勝浦での滞在時間は約3時間半です。
.
今回はここまで。本日もありがとうございました。
.



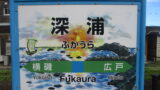


コメント